ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
価格競争から抜け出すために、5分でわかるマーケティングと営業のキモについて解説します。
- トップページ
- ブログ個人トップ
前ページ
次ページ
2009年04月14日(火)更新
「お客さんは誰か?」を理解するということ
こんにちは。マーケティング・トルネードの佐藤昌弘です。
私は、集客やセールスの分野における専門家として、
理論だけではなく、実務レベルでお手伝いをするのが仕事です。
最終的なアウトプットとしては、具体的にいえば、ホームページの
リニューアルや、チラシの添削、新聞広告や、道路看板などの
デザインや大きさにまでアドバイスをしていきます。
集客やセールス分野においては、抽象的な方向性だけを示しても、
結果につながらなければ時間も労力もお金ももったいないからです。
さて、そうした日々の仕事の中で、いつも繰り返し経験する
トピックについて、今日はお話しします。
それは、「業績を回復させたい人や、業績を伸ばしたい人にとって、
避けては通れないテーマ」についてです。
クライアント企業さんからの相談はいろいろあります。
次の新商品開発へのアドバイスをください。営業研修をしてください。
集客イベントのチラシにアドバイスください。それこそ千差万別です。
しかし、いつも質問することがあるんです。
それは、「どんな客なのか? 客は誰か?」という質問です。
なぜかといえば、「どんな客なのか? 客は誰か?」ということを
ちゃんと理解することが、とても重要だからにほかなりません。
ここで誤解が生じるわけです。
私が「客は誰か?」という質問の仕方をするからといって、
なるほどね、と思ってはいけないのです。
「なんだそれ? 自分で質問しておいて、そのまま質問に
答えようとするなだと? 何だ、それは?」
とお叱りを受けるのは仕方がありません。だけど本当のことなのです。
これは、私の文章力の無さが原因なのですが、職人さんを相手にすると、
よく生じることなのです。
例えば、お寿司が上手になりたいとします。
そして、その道の専門家へと訊ねたとします。
『お寿司のコツはね、 「どんな魚のネタか」
を、ちゃんと理解することなんだよねえ』
ひとことで整理して伝えなければならないとか、わかりやすくしないと、
とか、どうしてもこうした場合には、言葉足らずにならざるを得ないのです。
私の場合には、特にそうです。
ですから、専門家にそう言われても、
「はいはい、わかりました」とは、言っちゃいけないと思うのです。
それだけで終わらずに、
「どんな魚のネタかを理解するって、どういうことですか?」
と根ほり葉ほり、突き詰めていくと、ようやく詳しく教えて
もらえたりするからです。
そうでもしないと、大事なところをわからないまま、
つい、言葉通り受け取って、わかったつもりになっちゃうのです。
そこで、私も自問自答をしてみることにしました。
『「どんな客なのか? 客は誰か?」ということをちゃんと理解すること』
とは、なにか?
「どんな客か」「客は誰か?」とは、どういうことなのか?
具体的なケーススタディで説明しましょう。
たとえば、私の場合であれば、ビジネス教材を販売していたりもします。
「凡人が最強営業マンに変わるセールスセミナーDVD」という
セールス実演DVDを販売していたりします。
そこで質問をするわけです。
「営業ノウハウDVDの教材を買われる人は、どんな客なのか?」
という質問です。
もちろん、これにはいろんな答え方があると思います。
1.「3か月、営業成績がタコ(0件)を打ち、
4か月目に突入しようとして、
いよいよせっぱつまってきている営業マン」
2.「社長業として営業活動もしている人」
3.「営業で売上に悩んでいる営業マン」
どれも本当ではあります。間違いではありません。
しかし、マーケティング的に役立つ答え方として適切なのは、
1番なのです。
2番も3番も、答えは、正しいのかも知れないが、マーケティング的には
役立たない可能性が高いのです。
1番をご覧ください。
お客さんを語る言葉のなかに、消費の動機が語られていることが
おわかり頂けると思います。
「3か月連続で成績タコになり、せっぱつまった」のは、
確かに何らかの行動を起こすに十分な動機を感じさせませんか?
こういうのが、「顧客とは誰か?」と考えたときの、ちゃんとした
答えだと思うのです。
購入動機と一緒にお客さんをイメージするのは、極めて大事なことです。
ぜひ、ご参考にして頂ければ幸いです。
私は、集客やセールスの分野における専門家として、
理論だけではなく、実務レベルでお手伝いをするのが仕事です。
最終的なアウトプットとしては、具体的にいえば、ホームページの
リニューアルや、チラシの添削、新聞広告や、道路看板などの
デザインや大きさにまでアドバイスをしていきます。
集客やセールス分野においては、抽象的な方向性だけを示しても、
結果につながらなければ時間も労力もお金ももったいないからです。
さて、そうした日々の仕事の中で、いつも繰り返し経験する
トピックについて、今日はお話しします。
それは、「業績を回復させたい人や、業績を伸ばしたい人にとって、
避けては通れないテーマ」についてです。
クライアント企業さんからの相談はいろいろあります。
次の新商品開発へのアドバイスをください。営業研修をしてください。
集客イベントのチラシにアドバイスください。それこそ千差万別です。
しかし、いつも質問することがあるんです。
それは、「どんな客なのか? 客は誰か?」という質問です。
なぜかといえば、「どんな客なのか? 客は誰か?」ということを
ちゃんと理解することが、とても重要だからにほかなりません。
ここで誤解が生じるわけです。
私が「客は誰か?」という質問の仕方をするからといって、
なるほどね、と思ってはいけないのです。
「なんだそれ? 自分で質問しておいて、そのまま質問に
答えようとするなだと? 何だ、それは?」
とお叱りを受けるのは仕方がありません。だけど本当のことなのです。
これは、私の文章力の無さが原因なのですが、職人さんを相手にすると、
よく生じることなのです。
例えば、お寿司が上手になりたいとします。
そして、その道の専門家へと訊ねたとします。
『お寿司のコツはね、 「どんな魚のネタか」
を、ちゃんと理解することなんだよねえ』
ひとことで整理して伝えなければならないとか、わかりやすくしないと、
とか、どうしてもこうした場合には、言葉足らずにならざるを得ないのです。
私の場合には、特にそうです。
ですから、専門家にそう言われても、
「はいはい、わかりました」とは、言っちゃいけないと思うのです。
それだけで終わらずに、
「どんな魚のネタかを理解するって、どういうことですか?」
と根ほり葉ほり、突き詰めていくと、ようやく詳しく教えて
もらえたりするからです。
そうでもしないと、大事なところをわからないまま、
つい、言葉通り受け取って、わかったつもりになっちゃうのです。
そこで、私も自問自答をしてみることにしました。
『「どんな客なのか? 客は誰か?」ということをちゃんと理解すること』
とは、なにか?
「どんな客か」「客は誰か?」とは、どういうことなのか?
具体的なケーススタディで説明しましょう。
たとえば、私の場合であれば、ビジネス教材を販売していたりもします。
「凡人が最強営業マンに変わるセールスセミナーDVD」という
セールス実演DVDを販売していたりします。
そこで質問をするわけです。
「営業ノウハウDVDの教材を買われる人は、どんな客なのか?」
という質問です。
もちろん、これにはいろんな答え方があると思います。
1.「3か月、営業成績がタコ(0件)を打ち、
4か月目に突入しようとして、
いよいよせっぱつまってきている営業マン」
2.「社長業として営業活動もしている人」
3.「営業で売上に悩んでいる営業マン」
どれも本当ではあります。間違いではありません。
しかし、マーケティング的に役立つ答え方として適切なのは、
1番なのです。
2番も3番も、答えは、正しいのかも知れないが、マーケティング的には
役立たない可能性が高いのです。
1番をご覧ください。
お客さんを語る言葉のなかに、消費の動機が語られていることが
おわかり頂けると思います。
「3か月連続で成績タコになり、せっぱつまった」のは、
確かに何らかの行動を起こすに十分な動機を感じさせませんか?
こういうのが、「顧客とは誰か?」と考えたときの、ちゃんとした
答えだと思うのです。
購入動機と一緒にお客さんをイメージするのは、極めて大事なことです。
ぜひ、ご参考にして頂ければ幸いです。
株式会社マーケティング・トルネード
代表取締役
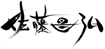
2009年04月07日(火)更新
来店型ビジネスが、チラシの反応率を上げる方法
こんにちは。
マーケティング・トルネードの一條です。
ここ、名古屋ではすっかり桜が満開。
弊社の窓からは、いたるところにやわらかなピンクのかたまりが見受けられます。
すっかり春、ですね。
さて、今日は来店型ビジネスのチラシの反応率を上げる方法について、
お話しすることにします。
というのも、チラシを前にして、「う~~~~んんんんん」
と悩んでいらっしゃる社長さんを見る機会が続いたからなんですね。
特に、来店型のビジネスをしていらっしゃる方にはお役に立てるはず。
それでは早速始めましょう。
■考えれば考えるほど、分からなく・・・
社長さんが自社のチラシを前にして、「う~~~~んんんんん」と悩む。
その理由はいろいろです。
例えば、ある社長さんは「チラシのキャッチコピーはどうすればいいか?」と
相談してこられます。
ある方は、「チラシに書く内容は、どうすればいいか?」と相談してこられます。
ある方は、「チラシの色はどうすれば?」と相談してこられます。
皆さん、勉強熱心な社長さんばかり。
それこそ、広告代理店の方以上に勉強していらっしゃる方もおられます。
しかし、皆さん、揃って、「う~~~~んんんんん」と唸ってしまう。
チラシのことを考えれば考えるほど、何が良いのか分からなくなるのです。
では、こんな時、どうすればいいのでしょう?
あなたが来店型のビジネスをされているなら、
とても簡単な打開策があります。
お客さまに、たったひとつ、「質問」を投げかけるのです。
そもそも、お客さまがあなたのお店に来る来店型ビジネスでは、
【チラシ】=【お客さまをお店に連れてくるためのツール】です。
ということは、チラシを見て、来店されたお客さまは、
「チラシの内容のどこかに興味を持ったから」来店したということになります。
だったら、お客さまに、興味を持った部分を聞いてしまえばいい。
とても単純な解決策なので、「な~んだ」と思われたかも知れませんが、
やってみたことのある方も驚くほど、少ない。
しかし、効果はお墨付きです。
お客さまへの質問は次の通りです。
「今回はこのチラシをご覧になって、ご来店頂いたわけなのですが、
このチラシのどの部分を見て、ご来店されることにされたのですか?」
この質問をお客さまが来店された際に聞いてみて下さい。
思ってもいなかった部分を指摘されることに驚かれるかも知れません。
例えばある薬局では、チラシの片隅に、ちいさーく書いてあった
「既存のお客さまからの質問」が、
一番注目を集めていたと分かったこともあります。
大きく目立つように書かれている部分が、興味を持たれているとは限りません。
小さく、小さく書いてある部分がきっかけで、お客さまが来店してくれていた
というケースは本当に多いのです。
■チラシの反応率を上げる、ネクストステップ
こうして、お客さまがチラシのどの部分に興味を持っていたのかが
わかった後は、次のステップです。
次のチラシを作る時に、前回のチラシでお客さまが興味を示していた部分を
大きく目立たせるのです。
ひょっとしたら、お客さまが興味を持った部分がキャッチコピーに
なるかも知れません。
いずれにしても、前回のチラシでお客さまが興味を持った部分を
大きくするだけで、チラシへの反応率は上がります。
そしてまた、2回目のチラシを見て来店された方に、
「どの部分に興味を持ったのか」を聞いていく。
とても地道な取り組みのように思えますが、かかる費用は、タダ。無料、ゼロ円。
なのに、社長がひとりでうんうん唸って考えるチラシよりも、
格段に反応率の高いチラシが手に入る。
チラシのキャッチコピーや内容でお悩みであれば、
是非、試してみて頂きたいと思います。
■質問の順番は?
さて、最後にひとつ。
この取り組みをする際には、次の順番で、お客さまに言葉をかけてみて下さい。
1.「今回、このチラシを見てご来店頂いたわけなのですが」
2.「このチラシのどの部分を見て、ご来店されることにされたのですか?」
詳しい理論は割愛しますが、この順番には、人間なら誰しもが持っている
『一貫性の法則』という心理法則が使われています。
この順番で、この質問をすることで、お客さまからの本音を
引き出しやすくなるのですね。
質問の際には、チラシの実物を見せながら質問することも忘れずに。
是非、良いヒントを手に入れて下さいね。
ではまた。
次回、この場所でお会いしましょう。
(追記)
文中でご紹介した『一貫性の法則』をもう少し掘り下げて知りたい
という方には、下記の2冊がお勧めです。
ご興味があれば、是非、どうぞ。
●『影響力の武器』(著:ロバート・B・チャルディーニ 誠信書房刊)
●『凡人が最強営業マンになる魔法のセールストーク』 (著:佐藤昌弘 日本実業出版社刊)
マーケティング・トルネードの一條です。
ここ、名古屋ではすっかり桜が満開。
弊社の窓からは、いたるところにやわらかなピンクのかたまりが見受けられます。
すっかり春、ですね。
さて、今日は来店型ビジネスのチラシの反応率を上げる方法について、
お話しすることにします。
というのも、チラシを前にして、「う~~~~んんんんん」
と悩んでいらっしゃる社長さんを見る機会が続いたからなんですね。
特に、来店型のビジネスをしていらっしゃる方にはお役に立てるはず。
それでは早速始めましょう。
■考えれば考えるほど、分からなく・・・
社長さんが自社のチラシを前にして、「う~~~~んんんんん」と悩む。
その理由はいろいろです。
例えば、ある社長さんは「チラシのキャッチコピーはどうすればいいか?」と
相談してこられます。
ある方は、「チラシに書く内容は、どうすればいいか?」と相談してこられます。
ある方は、「チラシの色はどうすれば?」と相談してこられます。
皆さん、勉強熱心な社長さんばかり。
それこそ、広告代理店の方以上に勉強していらっしゃる方もおられます。
しかし、皆さん、揃って、「う~~~~んんんんん」と唸ってしまう。
チラシのことを考えれば考えるほど、何が良いのか分からなくなるのです。
では、こんな時、どうすればいいのでしょう?
あなたが来店型のビジネスをされているなら、
とても簡単な打開策があります。
お客さまに、たったひとつ、「質問」を投げかけるのです。
そもそも、お客さまがあなたのお店に来る来店型ビジネスでは、
【チラシ】=【お客さまをお店に連れてくるためのツール】です。
ということは、チラシを見て、来店されたお客さまは、
「チラシの内容のどこかに興味を持ったから」来店したということになります。
だったら、お客さまに、興味を持った部分を聞いてしまえばいい。
とても単純な解決策なので、「な~んだ」と思われたかも知れませんが、
やってみたことのある方も驚くほど、少ない。
しかし、効果はお墨付きです。
お客さまへの質問は次の通りです。
「今回はこのチラシをご覧になって、ご来店頂いたわけなのですが、
このチラシのどの部分を見て、ご来店されることにされたのですか?」
この質問をお客さまが来店された際に聞いてみて下さい。
思ってもいなかった部分を指摘されることに驚かれるかも知れません。
例えばある薬局では、チラシの片隅に、ちいさーく書いてあった
「既存のお客さまからの質問」が、
一番注目を集めていたと分かったこともあります。
大きく目立つように書かれている部分が、興味を持たれているとは限りません。
小さく、小さく書いてある部分がきっかけで、お客さまが来店してくれていた
というケースは本当に多いのです。
■チラシの反応率を上げる、ネクストステップ
こうして、お客さまがチラシのどの部分に興味を持っていたのかが
わかった後は、次のステップです。
次のチラシを作る時に、前回のチラシでお客さまが興味を示していた部分を
大きく目立たせるのです。
ひょっとしたら、お客さまが興味を持った部分がキャッチコピーに
なるかも知れません。
いずれにしても、前回のチラシでお客さまが興味を持った部分を
大きくするだけで、チラシへの反応率は上がります。
そしてまた、2回目のチラシを見て来店された方に、
「どの部分に興味を持ったのか」を聞いていく。
とても地道な取り組みのように思えますが、かかる費用は、タダ。無料、ゼロ円。
なのに、社長がひとりでうんうん唸って考えるチラシよりも、
格段に反応率の高いチラシが手に入る。
チラシのキャッチコピーや内容でお悩みであれば、
是非、試してみて頂きたいと思います。
■質問の順番は?
さて、最後にひとつ。
この取り組みをする際には、次の順番で、お客さまに言葉をかけてみて下さい。
1.「今回、このチラシを見てご来店頂いたわけなのですが」
2.「このチラシのどの部分を見て、ご来店されることにされたのですか?」
詳しい理論は割愛しますが、この順番には、人間なら誰しもが持っている
『一貫性の法則』という心理法則が使われています。
この順番で、この質問をすることで、お客さまからの本音を
引き出しやすくなるのですね。
質問の際には、チラシの実物を見せながら質問することも忘れずに。
是非、良いヒントを手に入れて下さいね。
ではまた。
次回、この場所でお会いしましょう。
マーケティング・トルネード
一條仁志
(追記)
文中でご紹介した『一貫性の法則』をもう少し掘り下げて知りたい
という方には、下記の2冊がお勧めです。
ご興味があれば、是非、どうぞ。
●『影響力の武器』(著:ロバート・B・チャルディーニ 誠信書房刊)
●『凡人が最強営業マンになる魔法のセールストーク』 (著:佐藤昌弘 日本実業出版社刊)
2009年03月25日(水)更新
「なんだか凄い」を、「やっぱり凄い」に変えるために。
こんにちは。
マーケティングトルネードの巽です。
少し古い話ですが、動画共有サイトで話題になった作品をご存知でしょうか?
「あの曲とこの曲はよく似ている。
なぜなら、同じコード進行が使われているから。」
コード進行とは、「楽曲のメロディーを支配する伴奏の流れ」のことです。
動画の主は、往年のヒット曲を次々に引き合いに出しながら、
それぞれの楽曲同士が似通ってしまう構造的な理由を
分かりやすく解説していきます。
この動画は商用目的で作られたものではなさそうなので、
作者のちょっとした遊び心だったのかも知れませんが、
その反響は凄まじく、主要なニュースサイトでも取り上げられるほどでした。
さて、この動画で語られていた内容は、
音楽を多少かじったことのある人間ならば、
特に珍しい話ではなかったと思います。
しかし、その動画に寄せられたコメントの数々は、
音楽の玄人たちには、驚きだったに違いありません。
「え? それって、そんなに新鮮な話だったわけ?」
「これだけカラオケで歌われておきながら、今まで気がつかなかったってことなのか?」
そんな風に感じた人も多かったはずです。
動画の主が伝えたかったメッセージは分かりませんが、
この動画の反響から学べることは、2つあります。
ひとつは、適切な伝え方を選択することで、その効果は大きくなるということ。
もうひとつは、あなたが当たり前だと思っていることは、
思い込みに過ぎないかも知れないということです。
前回のコラムで私は、
「同業に笑われるくらいでちょうどいい」という趣旨のお話をしました。
これは、
「お客さんは無知だと思え」と言いたいわけではく、
「誰でも知っているようなことしか話さなくてもいい」と言いたいわけでもありません。
むしろその逆で、「せっかくの知識を、難しいまま伝えてしまう」ことが引き起こす、
機会損失を問いたかったのです。
例をあげてみましょう。
・創業200年
・貴重な●●●配合
・●●●特許取得済み
・業界初の●●機能搭載
・累計●●万部突破
・世界的権威からの推薦済み
なんだか凄そうですね。
でも、それがどう凄いのかについては、
「なんとなく」でしか伝わっていないと考えた方が無難です。
なぜなら、その業界に生きていないお客さんに対して、
それがどんなに凄いことなのかを理解してもらうには、
その凄さを説明してあげる必要があるからです。
先に挙げた動画共有サイトでの反響は、
分かりやすく伝えることによる「可能性」を物語るものです。
「こんな当たり前のことを書いたら、同業者に笑われるかもしれない」
そう思っているのは、あなたとあなたの同業者だけかも知れません。
「なんだか凄い」を、「やっぱり凄い」に変えるのも、
あなたの仕事なのです。
追伸:
私の原稿を、「より分かりやすい文章にする」お手伝いをしてくださる
編集者さんには、いつも感謝しています。
マーケティングトルネードの巽です。
少し古い話ですが、動画共有サイトで話題になった作品をご存知でしょうか?
「あの曲とこの曲はよく似ている。
なぜなら、同じコード進行が使われているから。」
コード進行とは、「楽曲のメロディーを支配する伴奏の流れ」のことです。
動画の主は、往年のヒット曲を次々に引き合いに出しながら、
それぞれの楽曲同士が似通ってしまう構造的な理由を
分かりやすく解説していきます。
この動画は商用目的で作られたものではなさそうなので、
作者のちょっとした遊び心だったのかも知れませんが、
その反響は凄まじく、主要なニュースサイトでも取り上げられるほどでした。
さて、この動画で語られていた内容は、
音楽を多少かじったことのある人間ならば、
特に珍しい話ではなかったと思います。
しかし、その動画に寄せられたコメントの数々は、
音楽の玄人たちには、驚きだったに違いありません。
「え? それって、そんなに新鮮な話だったわけ?」
「これだけカラオケで歌われておきながら、今まで気がつかなかったってことなのか?」
そんな風に感じた人も多かったはずです。
動画の主が伝えたかったメッセージは分かりませんが、
この動画の反響から学べることは、2つあります。
ひとつは、適切な伝え方を選択することで、その効果は大きくなるということ。
もうひとつは、あなたが当たり前だと思っていることは、
思い込みに過ぎないかも知れないということです。
前回のコラムで私は、
「同業に笑われるくらいでちょうどいい」という趣旨のお話をしました。
これは、
「お客さんは無知だと思え」と言いたいわけではく、
「誰でも知っているようなことしか話さなくてもいい」と言いたいわけでもありません。
むしろその逆で、「せっかくの知識を、難しいまま伝えてしまう」ことが引き起こす、
機会損失を問いたかったのです。
例をあげてみましょう。
・創業200年
・貴重な●●●配合
・●●●特許取得済み
・業界初の●●機能搭載
・累計●●万部突破
・世界的権威からの推薦済み
なんだか凄そうですね。
でも、それがどう凄いのかについては、
「なんとなく」でしか伝わっていないと考えた方が無難です。
なぜなら、その業界に生きていないお客さんに対して、
それがどんなに凄いことなのかを理解してもらうには、
その凄さを説明してあげる必要があるからです。
先に挙げた動画共有サイトでの反響は、
分かりやすく伝えることによる「可能性」を物語るものです。
「こんな当たり前のことを書いたら、同業者に笑われるかもしれない」
そう思っているのは、あなたとあなたの同業者だけかも知れません。
「なんだか凄い」を、「やっぱり凄い」に変えるのも、
あなたの仕事なのです。
追伸:
私の原稿を、「より分かりやすい文章にする」お手伝いをしてくださる
編集者さんには、いつも感謝しています。
株式会社マーケティングトルネード
巽大平
2009年03月19日(木)更新
広告に写真・イラストは使うべき?
マーケティング・トルネード佐藤です。
今日は、広告とデザインの話です。
広告を出そうと思うとき、どんな社長でも迷います。
何に迷うのか?
お金を払って効果が無ければ、まったくの無駄遣いになるのを
知っているから投資を迷うのです。
そして、広告投資で失敗しないために、専門家に
相談しようとします。
すると、昔から言われている事柄を言われます。
『広告はブランドづくりのためにも、イメージを大切にするべし』
『そのためにも写真やイラストを工夫しなければならない』
『知名度を上げるためには、何度も、繰り返し、回数を多く広告を』
誰でも、なるほどね、と唸ります。
どれも正しく聞こえますから。
本当に正しいのでしょうか?
これ、正しいのです。
意外でしたか?
私は、イメージの良さは不要だとは思いません。
会社のイメージは良いに越したことはないからです。
私は、写真やイラストを広告に使うのが無駄だと思いません。
写真やイラストのほうが、文字よりも、より多くのメッセージを
伝える力を持っているのは事実だからです。
私は、認知度の高さが不要だとは言いません。
知名度が高ければ高いほど、購入してもらえることは、
データが証明しています。
しかし、私は安易にそれを薦めたりもしません。
なぜなら、「儲かる以上にお金がかかる」からです。
イメージ重視の広告を作って、多頻度で出す。
それをやると、多額のコストがかかります。
でも、そうしたコストを超える利益が生まれてくるのであれば、
じゃんじゃんやるべきなのです。
ところが、今の時代、なかなかそうはいきません。
多くの企業にとって、広告は、
「儲かる以上に金がかかる」という状況なのです。
では、我々中小企業はどうすればいいのでしょうか?
あなたはどう考えたら良いのでしょうか?
これへの答えはもちろんひとつじゃありません。
しかし、大事なことをひとつ伝えるとすれば、これです。
『今こそ、「何を伝えるか?」に集中して欲しい』
ということです。
簡単な例をあげましょう。
仮に、「笑顔教室」というビジネスを運営している会社があったとします。
そこで「笑顔が素敵な笑顔の先生」が広告を出したとします。
だけど、これだと儲かりそうもないですよね。
あなたも、「それで売れるの?」と心配になるはずです。
しかし、「JALが笑顔を学びに来る、笑顔の先生」と内容が変わったとします。
そうすると、とたんに先ほどよりも売れるにおいがしてきませんか?
さらに、「JALが笑顔を学びに来る、笑顔の先生。就職面接セミナー」
となると、どうでしょうか。
架空のビジネスですが、先ほどよりも、さらに売れる気配が増します。
なぜでしょうか?
どうして売れる気配が増すのでしょうか?
それは「何を伝えるか」の「何」を考えているからです。
写真やイラストは、「どう伝えるか」の「手法」なのです。
この「笑顔の先生」の広告を作るとき、笑顔を表現する方法として、
イラストの方が効果的なら、イラストを使えばいい。
笑顔の写真を掲載したほうが効果的になるのなら、写真を使えばいい。
しかし、「何を伝えるか」の部分を、置き去りにしたまま、写真を使うべきか、
イラストは効果的か、を議論しても無益なのです。
『広告はブランドづくりのためにも、イメージを大切にするべし』
『そのためにも写真やイラストを工夫しなければならない』
『知名度を上げるためには、何度も、繰り返し、回数を多く広告を』
これは正しいですが、今のようなシビアな時代は、
それ以前に、「何を」をしっかり考えるのが大事です。
ぜひ、広告作りの際に、少しだけ思い出して欲しいです。
今日は、広告とデザインの話です。
広告を出そうと思うとき、どんな社長でも迷います。
何に迷うのか?
お金を払って効果が無ければ、まったくの無駄遣いになるのを
知っているから投資を迷うのです。
そして、広告投資で失敗しないために、専門家に
相談しようとします。
すると、昔から言われている事柄を言われます。
『広告はブランドづくりのためにも、イメージを大切にするべし』
『そのためにも写真やイラストを工夫しなければならない』
『知名度を上げるためには、何度も、繰り返し、回数を多く広告を』
誰でも、なるほどね、と唸ります。
どれも正しく聞こえますから。
本当に正しいのでしょうか?
これ、正しいのです。
意外でしたか?
私は、イメージの良さは不要だとは思いません。
会社のイメージは良いに越したことはないからです。
私は、写真やイラストを広告に使うのが無駄だと思いません。
写真やイラストのほうが、文字よりも、より多くのメッセージを
伝える力を持っているのは事実だからです。
私は、認知度の高さが不要だとは言いません。
知名度が高ければ高いほど、購入してもらえることは、
データが証明しています。
しかし、私は安易にそれを薦めたりもしません。
なぜなら、「儲かる以上にお金がかかる」からです。
イメージ重視の広告を作って、多頻度で出す。
それをやると、多額のコストがかかります。
でも、そうしたコストを超える利益が生まれてくるのであれば、
じゃんじゃんやるべきなのです。
ところが、今の時代、なかなかそうはいきません。
多くの企業にとって、広告は、
「儲かる以上に金がかかる」という状況なのです。
では、我々中小企業はどうすればいいのでしょうか?
あなたはどう考えたら良いのでしょうか?
これへの答えはもちろんひとつじゃありません。
しかし、大事なことをひとつ伝えるとすれば、これです。
『今こそ、「何を伝えるか?」に集中して欲しい』
ということです。
簡単な例をあげましょう。
仮に、「笑顔教室」というビジネスを運営している会社があったとします。
そこで「笑顔が素敵な笑顔の先生」が広告を出したとします。
だけど、これだと儲かりそうもないですよね。
あなたも、「それで売れるの?」と心配になるはずです。
しかし、「JALが笑顔を学びに来る、笑顔の先生」と内容が変わったとします。
そうすると、とたんに先ほどよりも売れるにおいがしてきませんか?
さらに、「JALが笑顔を学びに来る、笑顔の先生。就職面接セミナー」
となると、どうでしょうか。
架空のビジネスですが、先ほどよりも、さらに売れる気配が増します。
なぜでしょうか?
どうして売れる気配が増すのでしょうか?
それは「何を伝えるか」の「何」を考えているからです。
写真やイラストは、「どう伝えるか」の「手法」なのです。
この「笑顔の先生」の広告を作るとき、笑顔を表現する方法として、
イラストの方が効果的なら、イラストを使えばいい。
笑顔の写真を掲載したほうが効果的になるのなら、写真を使えばいい。
しかし、「何を伝えるか」の部分を、置き去りにしたまま、写真を使うべきか、
イラストは効果的か、を議論しても無益なのです。
『広告はブランドづくりのためにも、イメージを大切にするべし』
『そのためにも写真やイラストを工夫しなければならない』
『知名度を上げるためには、何度も、繰り返し、回数を多く広告を』
これは正しいですが、今のようなシビアな時代は、
それ以前に、「何を」をしっかり考えるのが大事です。
ぜひ、広告作りの際に、少しだけ思い出して欲しいです。
株式会社マーケティング・トルネード
代表取締役
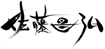
2009年03月18日(水)更新
「新事業」より「芯事業」
マーケティング・トルネードの一條です。
前回、新規事業の立ち上げ方について書いたのですが、
さっそく、コメントを頂きました。
こうやってコメントを頂くと、頑張って書いている甲斐があるというもの。
今日も、はりきって書きますね。
■「新事業」より「芯事業」
さて、前回頂いたコメントはとても興味深いものでした。
まずは頂いたコメントをご紹介します。
> 当社も今までに培った技術、資料などを資源として、お客様が
> どのようなことに興味をもたれているか、とりあえずサイトでテスト
> していますが、非常に反応があります。「新事業」より、まず「芯事業」
> かもしれません。ありがとうございました。
いったい、自社の芯となる事業は、何なのか?
私も、「自社の芯となる事業が分からない」とご相談を受ける
ケースがあります。
なんとなく売上は上がっている。
けれど、「弊社は○○に強い会社です!」と言える○○は
無いような気がする・・・。
このような状況なのですが、しかし、だからと言って、
これらの会社さんに「芯事業」がないということではありません。
ではなぜ、芯がないように感じるのか?
少し、お話ししていきましょう。
今日のテーマは、御社の芯事業を見つける方法です。
■すべてが違う事業だった
今の事業はあるし、売上も上がっている。
それなのになぜ、自社には芯がないと感じるのか?
それは『複数の事業を、ひとつの事業として捉えているから』かも知れません。
弊社ではマーケティングの基本として、事業を、【お客さん】【商品】
【販売方法】の3つの要素の掛け算で考えることをお勧めしています。
・お客は誰か?
・商品は何か?
・どうやって売っているのか?
この3つの要素です。
御社のお客さんは、法人なのか個人なのか?
法人であれば、どんな業種なのか? どれくらいの規模なのか?
個人であれば、男性なのか、女性なのか? 大人なのか、子供なのか?
地域に偏りはあるのか?
商品は何か。サービスなのか、モノなのか?
販売の方法は、対面販売なのか? 店舗に来てもらうのか?
営業で相手を訪問するのか? コールセンターを使うのか、
インターネットでの通販なのか?
例えば、【お茶】を販売している会社があります。
・この会社では、営業マンが法人を回ってお茶の注文を取っています(A)
・この会社では、新聞にチラシを折り込んで、電話でお茶の注文を
受け付けています(B)
・この会社では、インターネットのホームページからお茶の注文を
受け付けています(C)
ここで質問です。
この会社には、いくつの事業があるでしょう?
「え?事業って言ったって、お茶を売る事業、ひとつだけなんじゃ・・・」
そう考えるのも無理はありません。
だって、商品は【お茶】ひとつだからです。
しかし、思い出して頂きたいのです。
先ほど事業は、【お客さん】【商品】【販売の方法】の3つの要素の
掛け算で出来ているとお話ししました。
つまり、この3つのうちのひとつでも変われば、今まで通用していた
ノウハウは通用しなくなるのです。
例えば、法人営業用の営業トークは、個人のお客さまからかかってきた
電話を受けるコールセンターのトークには使えません。
ホームページの申込ボタンをどこに配置すればいいのかという
ノウハウは、新聞折り込みチラシのノウハウとはまた別のノウハウです。
今、上記のA、B、Cのそれぞれで売上が上がっているのであれば、
この会社にはA、B、Cの3つの事業のノウハウがあるということなのです。
しかし、もし仮にこの3つの事業を、【お茶を販売する】というひとつの
事業だと捉えていたとしたら?
それぞれのノウハウがごちゃごちゃになって、混乱してしまうかも
知れません。
その結果、「うちには芯となる事業がない・・・」と思う社長さんが
いてもおかしくはない。
しかし、芯がないわけではないのです。
そこで、御社の芯事業を見つけるために、まずやってみて頂きたい
ことがあります。とても簡単な2つのステップです。
ステップ1.
まず、今のお客さん、今の商品、今の販売方法をそれぞれ書き出してみる。
ステップ2.
全部書き出したら、お客さんと商品と販売方法の【3点セット】の
組み合わせをすべて書き出す。
これだけ。
【お客さん】が違えば、それも別事業として書き出します。
【お客さん】と【商品】が同じでも、【販売方法】が違えば、別事業です。
こうして分解した結果、自社の中にはいくつもの【3点セット】が
あることに気付かれた方もいらっしゃるかも知れません。
この過程でどの【3点セット】が伸びているのか、テコ入れをするべき
【3点セット】はどれなのか、これから育てたい【3点セット】は
どれなのかもはっきりしてきます。
あとは、それぞれの【3点セット】に対して、必要な取り組みを
していけばいい。
私は、御社の中には、芯となる事業はいくつもあると思っていますし、
いくつあってもいいものだとも思います。
そして、それらの芯は、優先順位が入れ替わったり、
形を変えたりしながら、御社を支えていく。
是非、御社の中にある【3点セット】のひとつひとつに光を
当ててみて頂きたいと思っています。
それではまた次回、この場所でお会いしましょう。
前回、新規事業の立ち上げ方について書いたのですが、
さっそく、コメントを頂きました。
こうやってコメントを頂くと、頑張って書いている甲斐があるというもの。
今日も、はりきって書きますね。
■「新事業」より「芯事業」
さて、前回頂いたコメントはとても興味深いものでした。
まずは頂いたコメントをご紹介します。
> 当社も今までに培った技術、資料などを資源として、お客様が
> どのようなことに興味をもたれているか、とりあえずサイトでテスト
> していますが、非常に反応があります。「新事業」より、まず「芯事業」
> かもしれません。ありがとうございました。
いったい、自社の芯となる事業は、何なのか?
私も、「自社の芯となる事業が分からない」とご相談を受ける
ケースがあります。
なんとなく売上は上がっている。
けれど、「弊社は○○に強い会社です!」と言える○○は
無いような気がする・・・。
このような状況なのですが、しかし、だからと言って、
これらの会社さんに「芯事業」がないということではありません。
ではなぜ、芯がないように感じるのか?
少し、お話ししていきましょう。
今日のテーマは、御社の芯事業を見つける方法です。
■すべてが違う事業だった
今の事業はあるし、売上も上がっている。
それなのになぜ、自社には芯がないと感じるのか?
それは『複数の事業を、ひとつの事業として捉えているから』かも知れません。
弊社ではマーケティングの基本として、事業を、【お客さん】【商品】
【販売方法】の3つの要素の掛け算で考えることをお勧めしています。
・お客は誰か?
・商品は何か?
・どうやって売っているのか?
この3つの要素です。
御社のお客さんは、法人なのか個人なのか?
法人であれば、どんな業種なのか? どれくらいの規模なのか?
個人であれば、男性なのか、女性なのか? 大人なのか、子供なのか?
地域に偏りはあるのか?
商品は何か。サービスなのか、モノなのか?
販売の方法は、対面販売なのか? 店舗に来てもらうのか?
営業で相手を訪問するのか? コールセンターを使うのか、
インターネットでの通販なのか?
例えば、【お茶】を販売している会社があります。
・この会社では、営業マンが法人を回ってお茶の注文を取っています(A)
・この会社では、新聞にチラシを折り込んで、電話でお茶の注文を
受け付けています(B)
・この会社では、インターネットのホームページからお茶の注文を
受け付けています(C)
ここで質問です。
この会社には、いくつの事業があるでしょう?
「え?事業って言ったって、お茶を売る事業、ひとつだけなんじゃ・・・」
そう考えるのも無理はありません。
だって、商品は【お茶】ひとつだからです。
しかし、思い出して頂きたいのです。
先ほど事業は、【お客さん】【商品】【販売の方法】の3つの要素の
掛け算で出来ているとお話ししました。
つまり、この3つのうちのひとつでも変われば、今まで通用していた
ノウハウは通用しなくなるのです。
例えば、法人営業用の営業トークは、個人のお客さまからかかってきた
電話を受けるコールセンターのトークには使えません。
ホームページの申込ボタンをどこに配置すればいいのかという
ノウハウは、新聞折り込みチラシのノウハウとはまた別のノウハウです。
今、上記のA、B、Cのそれぞれで売上が上がっているのであれば、
この会社にはA、B、Cの3つの事業のノウハウがあるということなのです。
しかし、もし仮にこの3つの事業を、【お茶を販売する】というひとつの
事業だと捉えていたとしたら?
それぞれのノウハウがごちゃごちゃになって、混乱してしまうかも
知れません。
その結果、「うちには芯となる事業がない・・・」と思う社長さんが
いてもおかしくはない。
しかし、芯がないわけではないのです。
そこで、御社の芯事業を見つけるために、まずやってみて頂きたい
ことがあります。とても簡単な2つのステップです。
ステップ1.
まず、今のお客さん、今の商品、今の販売方法をそれぞれ書き出してみる。
ステップ2.
全部書き出したら、お客さんと商品と販売方法の【3点セット】の
組み合わせをすべて書き出す。
これだけ。
【お客さん】が違えば、それも別事業として書き出します。
【お客さん】と【商品】が同じでも、【販売方法】が違えば、別事業です。
こうして分解した結果、自社の中にはいくつもの【3点セット】が
あることに気付かれた方もいらっしゃるかも知れません。
この過程でどの【3点セット】が伸びているのか、テコ入れをするべき
【3点セット】はどれなのか、これから育てたい【3点セット】は
どれなのかもはっきりしてきます。
あとは、それぞれの【3点セット】に対して、必要な取り組みを
していけばいい。
私は、御社の中には、芯となる事業はいくつもあると思っていますし、
いくつあってもいいものだとも思います。
そして、それらの芯は、優先順位が入れ替わったり、
形を変えたりしながら、御社を支えていく。
是非、御社の中にある【3点セット】のひとつひとつに光を
当ててみて頂きたいと思っています。
それではまた次回、この場所でお会いしましょう。
マーケティング・トルネード
一條仁志
| «前へ | 次へ» |
 ログイン
ログイン