ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)
価格競争から抜け出すために、5分でわかるマーケティングと営業のキモについて解説します。
- トップページ
- ブログ個人トップ
前ページ
次ページ
2009年10月06日(火)更新
売れば売るほど辛くなる? 繁盛店のパラドックス
いつもご愛読ありがとうございます。
マーケティング・トルネードの巽です。
先日、弊社がお世話になっている社労士の先生から、
訪問先の会社さんが運営しているネット販売サイトの相談を受けました。
女性用サニタリー用品の販売に特化したネットショップらしいのですが、
売上アップを目指してリニューアルを検討中だとのこと。
ただ、ネットショップのオーナーが集客や販売戦略に関する知識に乏しいため、
弊社のようなマーケティング屋の意見も聞いてみたいとのことで、
回りまわって当方にご質問くださったようでした。
さっそくサイトを覗いてみると、単価が数百円程度の商品ばかり。
おまけに、丈夫で長持ちという商品特性を持っていました。
一方、この商品に関する周辺キーワード単価は、すでに200~300円程度。
物販サイトのコンバージョン目標は、約1%程度とされていますので、
単純計算すると、3万円の広告費用をかけて数百円の利益が出る計算。
つまり、売れれば売れるほど赤字になっていくという悲惨な結果が待ち受けています。
もちろん、衝動買いも起こりえる商品単価ですから、
実際のコンバージョン率はもっと高くなるかもしれません。
しかし、着地先ページの構成が衝動買いを誘発させる「需要喚起型」では
なかったため、おそらく上記のような結果になるだろうと想像しました。
「このままでは難しい商売でしょうねぇ・・・」
今回の相談をお寄せくださった社労士の先生も、そう感じているようでした
でも、あきらめるには少し早いと思うのです。
なぜなら、「安く仕入れて高く売る」以外の解決策も、
探してみてほしいからです。
ネット販売の恐ろしい点は、表面上のマーケティング活動がまる見えだと
いうところ。ライバル店の「見掛け上の」仕掛けが即座に分かってしまう
PCネットの世界では、同じ商品を同じ方法で少しだけ安く売るライバルが
現れるだけで、すぐに商売が立ちいかなくなります。
商品を変更する。単価を高くする。仕入れ価格を下げる。広告費を圧縮する。
広告への反応率を上げる。人件費がかからないよう自動化する・・・。
通販サイトを運営していくには、どれも当たり前のように大切な取り組み
ですが、そうした努力だけでは追いつかないことが多いものです。
つまり、価格力だけに依存したマーケティングプランを組み立ててしまうと、
いくら有利な商品を扱っているつもりでも、どのみち消耗戦に陥ってしまうのです。
物販の平均コンバージョンレートは1%が平均。それならば、この
コンバージョンレートでも商売として成立しうるだけの仕組みを
考えてみてほしいのです。
販売商品と相性のいいオプション品を一緒に売る。
リピート性の高い高単価商品をまた買ってもらう。
オリジナル商品を開発して既存客にブランドスイッチを促す。
扱っている商品やサービス、環境、人材、リソースは会社によって
違いますから、100社あれば100通りの解決策があるはずです。
いかに早い段階で、「価格で勝負」だけの世界から抜け出すか。
それが、ネット販売業というゼロサムゲームで生き残っていくための
ポイントであることは、間違いないようです。
マーケティング・トルネードの巽です。
先日、弊社がお世話になっている社労士の先生から、
訪問先の会社さんが運営しているネット販売サイトの相談を受けました。
女性用サニタリー用品の販売に特化したネットショップらしいのですが、
売上アップを目指してリニューアルを検討中だとのこと。
ただ、ネットショップのオーナーが集客や販売戦略に関する知識に乏しいため、
弊社のようなマーケティング屋の意見も聞いてみたいとのことで、
回りまわって当方にご質問くださったようでした。
さっそくサイトを覗いてみると、単価が数百円程度の商品ばかり。
おまけに、丈夫で長持ちという商品特性を持っていました。
一方、この商品に関する周辺キーワード単価は、すでに200~300円程度。
物販サイトのコンバージョン目標は、約1%程度とされていますので、
単純計算すると、3万円の広告費用をかけて数百円の利益が出る計算。
つまり、売れれば売れるほど赤字になっていくという悲惨な結果が待ち受けています。
もちろん、衝動買いも起こりえる商品単価ですから、
実際のコンバージョン率はもっと高くなるかもしれません。
しかし、着地先ページの構成が衝動買いを誘発させる「需要喚起型」では
なかったため、おそらく上記のような結果になるだろうと想像しました。
「このままでは難しい商売でしょうねぇ・・・」
今回の相談をお寄せくださった社労士の先生も、そう感じているようでした
でも、あきらめるには少し早いと思うのです。
なぜなら、「安く仕入れて高く売る」以外の解決策も、
探してみてほしいからです。
ネット販売の恐ろしい点は、表面上のマーケティング活動がまる見えだと
いうところ。ライバル店の「見掛け上の」仕掛けが即座に分かってしまう
PCネットの世界では、同じ商品を同じ方法で少しだけ安く売るライバルが
現れるだけで、すぐに商売が立ちいかなくなります。
商品を変更する。単価を高くする。仕入れ価格を下げる。広告費を圧縮する。
広告への反応率を上げる。人件費がかからないよう自動化する・・・。
通販サイトを運営していくには、どれも当たり前のように大切な取り組み
ですが、そうした努力だけでは追いつかないことが多いものです。
つまり、価格力だけに依存したマーケティングプランを組み立ててしまうと、
いくら有利な商品を扱っているつもりでも、どのみち消耗戦に陥ってしまうのです。
物販の平均コンバージョンレートは1%が平均。それならば、この
コンバージョンレートでも商売として成立しうるだけの仕組みを
考えてみてほしいのです。
販売商品と相性のいいオプション品を一緒に売る。
リピート性の高い高単価商品をまた買ってもらう。
オリジナル商品を開発して既存客にブランドスイッチを促す。
扱っている商品やサービス、環境、人材、リソースは会社によって
違いますから、100社あれば100通りの解決策があるはずです。
いかに早い段階で、「価格で勝負」だけの世界から抜け出すか。
それが、ネット販売業というゼロサムゲームで生き残っていくための
ポイントであることは、間違いないようです。
株式会社マーケティングトルネード
巽大平
2009年09月18日(金)更新
タダで出来る営業力強化
営業部が個人事業主のあつまりのようになっている。
このようなご相談を受けることが続いています。
もちろん、それぞれの営業マンが成果を出し、営業部門全体の成果も
出ている時にはこのスタイルでもいいと思うのです。
一方で、世の中全体の流れが滞り、営業マンが成果を出しにくい状況に
なっている時には、このスタイルには問題がある。
今日は、【組織の力】を最大限に活かす営業チームを作る方法をお伝えします。
それでは早速始めましょう。
※今回のコラムでは、便宜上、『組織』という言葉を使っています。
なんだか、硬い言葉でもありますので、ご自身の状況にあわせて、チームや
部門などに読み替えて読んで頂ければうれしいです。
■とある営業組織の悩み
今、とあるフランチャイズチェーンさんに営業の研修をご提供しています。
この中で、本部の方からご相談を受けました。
本部の営業チームが個人事業主のあつまりのようになってしまったというのです。
本部の営業マンは、フランチャイズの加盟店さんのサポートが仕事です。
加盟店さんには、イケイケ営業の会社もあれば、比較的おとなしめの
会社もありますし、その地域もバラバラ。本部の営業マンは本部の
事務所にいる時間もほとんどない。
このような状況の中で、本部の営業チームが個人事業主のあつまりのように
なってしまったというのです。当然、社内での情報共有も、ノウハウの共有も
出来ていない。
このコラムを読んでくださっている方の中には、同じような状況を
抱えている会社さんもいらっしゃるかも知れません。
これは実にもったいない話です。
なぜなら、複数の営業マンが所属する営業チームには、個人事業主さんの
元に集まってくる何倍もの情報が集まってくるからです
チーム内で情報やノウハウの共有が出来れば、ライバルよりも一歩も
二歩も先に行くことが出来る。
では、どうやって営業マン同士の情報やノウハウを共有すればいいのか。
そのコツは、営業マン同士が使える『共通の言葉』をつくることです。
初めて聞く方もいらっしゃると思うので、少し説明させて下さい。
■共通の言葉とは?
『共通の言葉』というとなんだかむずかしそうです。
簡単に言うとこれは、お互いが、同じ意味で理解できる言葉のことです。
例えば、「法人税」という言葉があります。
しかし、社長と経理担当者とではこの言葉に対する理解の仕方が違います。
一方で、同じ規模の会社を経営している社長さん同士であれば、
比較的同じような理解が出来るかも知れません。
これが『共通の言葉』です。
大切なことは、その言葉自体の意味ではなく、話をしている相手が
その言葉について同じ理解を持てていること。
なぜなら、相手の言葉が理解できなければ、相手のことを理解する
気もなくなりますが、同じ言葉で話すようになると、「意外と
同じようなことで悩んでるんだな」とか、「ああ、そういうことが
言いたかったのか」とか分かることも増えてくるからです。
そうなると、お互いに助け合ったり、情報を提供し合ったりも出来るようになる。
『共通の言葉』を作る方法はいろいろです。
例えば、『チャレンジ』という会社方針を持っている会社であれば、
営業マン全員を集めた上で、「『チャレンジ』という言葉を別の言葉で
言うとどうなる?」という質問をしてみてもいいかも知れません。
その答えを聞くだけでも、「あ、アイツはこういう捉え方をしていたんだ」とか
「あの捉え方はいいな」とか、いろいろとお互いに気がつくことは出るはずです。
ただ単に社長が朝礼で「ウチの会社の方針は『チャレンジ』だ。みんな、
チャレンジするように!」と言っただけでは伝わらないことも、
こういう取り組みをすれば、チームのメンバー全員で共有できるようになる。
『共通の言葉』の出来上がりです。
より具体的に営業上の課題を通して、『共通の言葉』を作ることも出来ます。
その際には、弊社の代表佐藤が書いた『凡人が最強チームに変わる魔法の
営業ミーティング』(日本実業出版社刊)も参考にして頂けるかも知れません。
どんな方法を使ってでもいいから、営業チームの中に『共通の言葉』を作っていく。
しかも、この取り組みをするのにコストはかかりません。
タダ、無料、ノーチャージです。
でも、ボディーブローのようにジワジワ効果が出てくる。
営業組織が個人事業主のあつまりのようになってしまったという
会社さんにはお薦めしたい取り組みです。
■最後に
さて、ここまで、組織の力を活かすためには何を大事にすればいいのか、
私に分かる範囲のことをお伝えしてきました。
私自身も個人事業主になった経験があるからこそ言いますが、
個人事業主から見れば、組織で仕事が出来るメリットというのは、
本当に大きいものです。
そして、不況と言われる今だからこそ、組織の強みが活きる。
このコラムが何らかの形で、御社のお役に立てれば、
こんなにうれしいことはありません。
ではまた次回、この場所でお会いできることを楽しみにしています。
このようなご相談を受けることが続いています。
もちろん、それぞれの営業マンが成果を出し、営業部門全体の成果も
出ている時にはこのスタイルでもいいと思うのです。
一方で、世の中全体の流れが滞り、営業マンが成果を出しにくい状況に
なっている時には、このスタイルには問題がある。
今日は、【組織の力】を最大限に活かす営業チームを作る方法をお伝えします。
それでは早速始めましょう。
※今回のコラムでは、便宜上、『組織』という言葉を使っています。
なんだか、硬い言葉でもありますので、ご自身の状況にあわせて、チームや
部門などに読み替えて読んで頂ければうれしいです。
■とある営業組織の悩み
今、とあるフランチャイズチェーンさんに営業の研修をご提供しています。
この中で、本部の方からご相談を受けました。
本部の営業チームが個人事業主のあつまりのようになってしまったというのです。
本部の営業マンは、フランチャイズの加盟店さんのサポートが仕事です。
加盟店さんには、イケイケ営業の会社もあれば、比較的おとなしめの
会社もありますし、その地域もバラバラ。本部の営業マンは本部の
事務所にいる時間もほとんどない。
このような状況の中で、本部の営業チームが個人事業主のあつまりのように
なってしまったというのです。当然、社内での情報共有も、ノウハウの共有も
出来ていない。
このコラムを読んでくださっている方の中には、同じような状況を
抱えている会社さんもいらっしゃるかも知れません。
これは実にもったいない話です。
なぜなら、複数の営業マンが所属する営業チームには、個人事業主さんの
元に集まってくる何倍もの情報が集まってくるからです
チーム内で情報やノウハウの共有が出来れば、ライバルよりも一歩も
二歩も先に行くことが出来る。
では、どうやって営業マン同士の情報やノウハウを共有すればいいのか。
そのコツは、営業マン同士が使える『共通の言葉』をつくることです。
初めて聞く方もいらっしゃると思うので、少し説明させて下さい。
■共通の言葉とは?
『共通の言葉』というとなんだかむずかしそうです。
簡単に言うとこれは、お互いが、同じ意味で理解できる言葉のことです。
例えば、「法人税」という言葉があります。
しかし、社長と経理担当者とではこの言葉に対する理解の仕方が違います。
一方で、同じ規模の会社を経営している社長さん同士であれば、
比較的同じような理解が出来るかも知れません。
これが『共通の言葉』です。
大切なことは、その言葉自体の意味ではなく、話をしている相手が
その言葉について同じ理解を持てていること。
なぜなら、相手の言葉が理解できなければ、相手のことを理解する
気もなくなりますが、同じ言葉で話すようになると、「意外と
同じようなことで悩んでるんだな」とか、「ああ、そういうことが
言いたかったのか」とか分かることも増えてくるからです。
そうなると、お互いに助け合ったり、情報を提供し合ったりも出来るようになる。
『共通の言葉』を作る方法はいろいろです。
例えば、『チャレンジ』という会社方針を持っている会社であれば、
営業マン全員を集めた上で、「『チャレンジ』という言葉を別の言葉で
言うとどうなる?」という質問をしてみてもいいかも知れません。
その答えを聞くだけでも、「あ、アイツはこういう捉え方をしていたんだ」とか
「あの捉え方はいいな」とか、いろいろとお互いに気がつくことは出るはずです。
ただ単に社長が朝礼で「ウチの会社の方針は『チャレンジ』だ。みんな、
チャレンジするように!」と言っただけでは伝わらないことも、
こういう取り組みをすれば、チームのメンバー全員で共有できるようになる。
『共通の言葉』の出来上がりです。
より具体的に営業上の課題を通して、『共通の言葉』を作ることも出来ます。
その際には、弊社の代表佐藤が書いた『凡人が最強チームに変わる魔法の
営業ミーティング』(日本実業出版社刊)も参考にして頂けるかも知れません。
どんな方法を使ってでもいいから、営業チームの中に『共通の言葉』を作っていく。
しかも、この取り組みをするのにコストはかかりません。
タダ、無料、ノーチャージです。
でも、ボディーブローのようにジワジワ効果が出てくる。
営業組織が個人事業主のあつまりのようになってしまったという
会社さんにはお薦めしたい取り組みです。
■最後に
さて、ここまで、組織の力を活かすためには何を大事にすればいいのか、
私に分かる範囲のことをお伝えしてきました。
私自身も個人事業主になった経験があるからこそ言いますが、
個人事業主から見れば、組織で仕事が出来るメリットというのは、
本当に大きいものです。
そして、不況と言われる今だからこそ、組織の強みが活きる。
このコラムが何らかの形で、御社のお役に立てれば、
こんなにうれしいことはありません。
ではまた次回、この場所でお会いできることを楽しみにしています。
マーケティング・トルネード
一條仁志
2009年09月08日(火)更新
定価よりも高く売れてしまう場所
いつもご愛読ありがとうございます。
マーケティング・トルネードの巽です。
定価1,000円の図書券を、1,030円で販売しているショップがあります。
しかも、相当の数を売っています。
なんでこんなことが可能なのか?
適切な場所と顧客を狙い撃つことで成功している事例として、
ひとつご紹介してみます。
ご存知の方も多いかと思いますが、楽天にはアフィリエイトという機能があります。
アフィリエイトとは、簡単にいえば「ご紹介システム」のこと。
Aさんが作成したアフィリエイトリンクを経由して商品が売れた場合、
紹介者であるAさんには、その販売金額に応じて成果報酬が発生します。
5,000円のゲームソフトをブログなどで紹介してBさんに売れた場合、
紹介者のAさんには、販売金額の1%である50円が報酬として手に入る
というわけですね。
ところが、楽天アフィリエイトの場合、その報酬が現金ではなく
「楽天ポイント」なのです。
楽天ポイントは楽天内のショップでしか使えないため、
何かを買うことでしかポイントを消化できません。
かといって、そんなにしょっちゅう液晶テレビなどの高額商品も
欲しくならないわけで、ポイントを持てあますほどの優秀な
楽天アフィリエイターたちは、自分で買った売れ筋商品をオークションで
転売するなりして換金作業を行っていたわけです。
その手間を考えれば、換金性に優れた図書券やギフト券を売ってくれる
金券ショップの存在は有り難いもの。
つまりこのショップは、楽天ポイントをもてあますアフィリエイターたちの
両替所のような役割を果たしていたのです。
しかも、このショップさん。
買物の合計金額が5,000円以上でなければ注文を受け付けないという制限付き。
それにもかかわらず、飛ぶように売れていくのは、
「誰に、何を、どこで」売るのかが、絶妙なバランスで成り立っている
面白い事例ですね。
弊社で提唱している思考モデルの中に、「マーケティングクローバー」という
考え方があります。
これは、『「誰に」「何を」「どんなやり方で」売るのかを考え、
もっとも適合するものから優先的に取りかかりましょう』という、
マーケティングをうまくやるためのコツを、弊社佐藤が図式化したものです。
「なぜあんな商売が成り立っているんだろう?」と不思議に思った時には、
必ずそこに何かしらの仕掛けがあります。
1.「誰に売っているのか」を考えてみること
2.「何を売っているのか」を考えてみること
3.「どのように売っているのか」を考えてみること
ある事象に出会ったとき、上記のような視点で見てみると、
マーケティングのトレーニングに役立つかもしれません。
さて、この話には続きがあります。
先日、楽天がある発表を行いました。
それは、2010年1月支払い分(2009年11月成果発生分)から、成果報酬で
3,000ポイントを超えた分は、オンライン電子マネー「楽天キャッシュ」での
支払いに対応するというもの。
つまり、楽天アフィリエイターは、手軽にポイントを換金できるようになるわけです。
「昨日有料だったものが、今日無料になる世界」
ビジネス上の突然死が起きるリスクが高いのも、ネットビジネスの怖さでもありますね。
マーケティング・トルネードの巽です。
定価1,000円の図書券を、1,030円で販売しているショップがあります。
しかも、相当の数を売っています。
なんでこんなことが可能なのか?
適切な場所と顧客を狙い撃つことで成功している事例として、
ひとつご紹介してみます。
ご存知の方も多いかと思いますが、楽天にはアフィリエイトという機能があります。
アフィリエイトとは、簡単にいえば「ご紹介システム」のこと。
Aさんが作成したアフィリエイトリンクを経由して商品が売れた場合、
紹介者であるAさんには、その販売金額に応じて成果報酬が発生します。
5,000円のゲームソフトをブログなどで紹介してBさんに売れた場合、
紹介者のAさんには、販売金額の1%である50円が報酬として手に入る
というわけですね。
ところが、楽天アフィリエイトの場合、その報酬が現金ではなく
「楽天ポイント」なのです。
楽天ポイントは楽天内のショップでしか使えないため、
何かを買うことでしかポイントを消化できません。
かといって、そんなにしょっちゅう液晶テレビなどの高額商品も
欲しくならないわけで、ポイントを持てあますほどの優秀な
楽天アフィリエイターたちは、自分で買った売れ筋商品をオークションで
転売するなりして換金作業を行っていたわけです。
その手間を考えれば、換金性に優れた図書券やギフト券を売ってくれる
金券ショップの存在は有り難いもの。
つまりこのショップは、楽天ポイントをもてあますアフィリエイターたちの
両替所のような役割を果たしていたのです。
しかも、このショップさん。
買物の合計金額が5,000円以上でなければ注文を受け付けないという制限付き。
それにもかかわらず、飛ぶように売れていくのは、
「誰に、何を、どこで」売るのかが、絶妙なバランスで成り立っている
面白い事例ですね。
弊社で提唱している思考モデルの中に、「マーケティングクローバー」という
考え方があります。
これは、『「誰に」「何を」「どんなやり方で」売るのかを考え、
もっとも適合するものから優先的に取りかかりましょう』という、
マーケティングをうまくやるためのコツを、弊社佐藤が図式化したものです。
「なぜあんな商売が成り立っているんだろう?」と不思議に思った時には、
必ずそこに何かしらの仕掛けがあります。
1.「誰に売っているのか」を考えてみること
2.「何を売っているのか」を考えてみること
3.「どのように売っているのか」を考えてみること
ある事象に出会ったとき、上記のような視点で見てみると、
マーケティングのトレーニングに役立つかもしれません。
さて、この話には続きがあります。
先日、楽天がある発表を行いました。
それは、2010年1月支払い分(2009年11月成果発生分)から、成果報酬で
3,000ポイントを超えた分は、オンライン電子マネー「楽天キャッシュ」での
支払いに対応するというもの。
つまり、楽天アフィリエイターは、手軽にポイントを換金できるようになるわけです。
「昨日有料だったものが、今日無料になる世界」
ビジネス上の突然死が起きるリスクが高いのも、ネットビジネスの怖さでもありますね。
株式会社マーケティングトルネード
巽大平
2009年09月01日(火)更新
小手先のテクニックに頼らない集客法とは
マーケティング・トルネード佐藤です。
ギフトショップの社長が、業績が悪化してきて、経営が苦しいと
嘆いていました。
彼は「どうやったら来店客数が増やせるのか」と、その方法を
知りたがっていたわけです。
今日は、この相談をキッカケにして、私がどんなアドバイスをしたのか?
それを簡略化して、お伝えしましょう。
ギフトショップにとって、集客をする方法は、いくつもある。
マスコミに取材してもらえる方法、
効果的な看板設置の方法、
新聞折り込みチラシの方法
既存客へダイレクトメールを送ってバックエンド品を売る方法
相乗りマーケティングという方法
業務提携先をご紹介するという方法
新商品の開発をするという方法
タレントさんに破格でお手伝い頂く方法
労力と予算と知恵によって、いくらでも方法はある。
私にとっては、毎日のようにそればかりアドバイスしているわけだから、
それほど難しいことでもない。
誰だって毎日やってれば、それなりに知識や経験や知恵もついてくるからだ。
しかし、それだけではいずれ限界が来るというのもわかっている。
だからこそ、伝えたかったことがあった。
それは、
「いつの日か、ギフトショップとして本質的に問われる時期が来る」
ということだ。
ギフトショップにとって、本質的な問いとは何だろうか?
それは「ギフト」というものへの深堀りである。
そもそもギフトとは何だろうか?
喜んでもらうためには何を贈れば良いのか?
感謝の意をギフトという贈り物で伝えるためにはどうすれば良いのか?
想いを伝えるためにはどうしたらいいのか?
そこで私はギフトショップオーナーに質問をしてみた。
「そもそも、ギフトの歴史って何ですか?」
「ギフトって、何のためにやってるんですか?」
「『気の利いたギフトってないの?』と質問されたとき、どうしていますか?
まさかタオルでお茶を濁そうとかしていませんか?」
ギフトの歴史・・・そんなもの、考えたことも無かった、という答えだった。
「それじゃいかんと思いますよ。これからの時代、特に、
ギフトとは、贈答とは、そうした本質的なところから、
しっかりと掘り下げて研究しておくことが大事になって
くると思います。それでこそプロだし、頼りにされるの
だと思うからです。単なるギフト品の小売店だけだと、
いずれ限界が来るような気がしています」
随分と生意気なことも言ったということは自覚している。
しかも、これはあくまでも私見でしかない。
しかし、ギフトという世界に、がっつり挑んでいるかどうかという
根本的な姿勢は、これからの時代に、必ず報われるような気がするのだ。
ギフト、贈り物の起源というものは何だろうか?
なぜ、人は贈答をするんだろうか?
贈答という行為に何を求めているのだろうか?
そのヒントを手にするためには、ギフトショップとして、
何を学べば良いのだろうか?
文化人類学? 社会心理学?
難しそうだけど、それが仕事に役立つのなら、ギフトの専門家になるために
役立つのなら、そこに、がっつり挑もう・・・という姿勢が大事になると思うのだ。
それを研究するために、果たして何か月必要だろうか。
夜な夜な情報収集や研究に時間を費やして、何年かかるだろうか。
ギフトに関連する本をアマゾンで全部買ったとして何冊になるんだろうか?
「小手先のテクニックでも集客は出来ますし、そのアドバイスはします。
だけども、そうした研究や専門性を高めるという努力をしてくれたら、
足腰が強い頼れるギフトショップになるし、場合によっては、
新商品の開発や監修、そうした新分野へ道を切り開いてくれるきっかけに
なるかも知れないですよ」
私は小手先のテクニックをアドバイスした上で、彼にそう伝えた。
しかしながら、これはギフトショップのオーナーに限った話ではない。
あらゆるビジネスが、こうした本質的なことを問われるように
なりつつある。
少々、説教臭い話かも知れないが、こんな話に何か感ずることがあれば幸いである。
ギフトショップの社長が、業績が悪化してきて、経営が苦しいと
嘆いていました。
彼は「どうやったら来店客数が増やせるのか」と、その方法を
知りたがっていたわけです。
今日は、この相談をキッカケにして、私がどんなアドバイスをしたのか?
それを簡略化して、お伝えしましょう。
ギフトショップにとって、集客をする方法は、いくつもある。
マスコミに取材してもらえる方法、
効果的な看板設置の方法、
新聞折り込みチラシの方法
既存客へダイレクトメールを送ってバックエンド品を売る方法
相乗りマーケティングという方法
業務提携先をご紹介するという方法
新商品の開発をするという方法
タレントさんに破格でお手伝い頂く方法
労力と予算と知恵によって、いくらでも方法はある。
私にとっては、毎日のようにそればかりアドバイスしているわけだから、
それほど難しいことでもない。
誰だって毎日やってれば、それなりに知識や経験や知恵もついてくるからだ。
しかし、それだけではいずれ限界が来るというのもわかっている。
だからこそ、伝えたかったことがあった。
それは、
「いつの日か、ギフトショップとして本質的に問われる時期が来る」
ということだ。
ギフトショップにとって、本質的な問いとは何だろうか?
それは「ギフト」というものへの深堀りである。
そもそもギフトとは何だろうか?
喜んでもらうためには何を贈れば良いのか?
感謝の意をギフトという贈り物で伝えるためにはどうすれば良いのか?
想いを伝えるためにはどうしたらいいのか?
そこで私はギフトショップオーナーに質問をしてみた。
「そもそも、ギフトの歴史って何ですか?」
「ギフトって、何のためにやってるんですか?」
「『気の利いたギフトってないの?』と質問されたとき、どうしていますか?
まさかタオルでお茶を濁そうとかしていませんか?」
ギフトの歴史・・・そんなもの、考えたことも無かった、という答えだった。
「それじゃいかんと思いますよ。これからの時代、特に、
ギフトとは、贈答とは、そうした本質的なところから、
しっかりと掘り下げて研究しておくことが大事になって
くると思います。それでこそプロだし、頼りにされるの
だと思うからです。単なるギフト品の小売店だけだと、
いずれ限界が来るような気がしています」
随分と生意気なことも言ったということは自覚している。
しかも、これはあくまでも私見でしかない。
しかし、ギフトという世界に、がっつり挑んでいるかどうかという
根本的な姿勢は、これからの時代に、必ず報われるような気がするのだ。
ギフト、贈り物の起源というものは何だろうか?
なぜ、人は贈答をするんだろうか?
贈答という行為に何を求めているのだろうか?
そのヒントを手にするためには、ギフトショップとして、
何を学べば良いのだろうか?
文化人類学? 社会心理学?
難しそうだけど、それが仕事に役立つのなら、ギフトの専門家になるために
役立つのなら、そこに、がっつり挑もう・・・という姿勢が大事になると思うのだ。
それを研究するために、果たして何か月必要だろうか。
夜な夜な情報収集や研究に時間を費やして、何年かかるだろうか。
ギフトに関連する本をアマゾンで全部買ったとして何冊になるんだろうか?
「小手先のテクニックでも集客は出来ますし、そのアドバイスはします。
だけども、そうした研究や専門性を高めるという努力をしてくれたら、
足腰が強い頼れるギフトショップになるし、場合によっては、
新商品の開発や監修、そうした新分野へ道を切り開いてくれるきっかけに
なるかも知れないですよ」
私は小手先のテクニックをアドバイスした上で、彼にそう伝えた。
しかしながら、これはギフトショップのオーナーに限った話ではない。
あらゆるビジネスが、こうした本質的なことを問われるように
なりつつある。
少々、説教臭い話かも知れないが、こんな話に何か感ずることがあれば幸いである。
株式会社マーケティング・トルネード
代表取締役
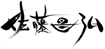
2009年08月04日(火)更新
イヤなお客さんと付き合わなくてもすむ方法
いつもありがとうございます。
マーケティング・トルネードの巽です。
今回も、クライアントさんからご相談頂いた
事例を紹介してみたいと思います。
石川県で、浴槽の再生事業を専門にされている、
バスメイクの津田さんというクライアントがいます。
浴槽の再生事業とは、早い話がお風呂周りの修理屋さん。
でも、普通の修理屋さんとは、ちょっと違うんです。
旅館やホテル、賃貸物件など、何十年間も利用されて老朽化した浴室や、
すでに修理の施しようがないほどに損傷してしまった浴槽本体を、
特殊な再生技術を使って、まるで新品と見間違えるような
補修作業してしまうエキスパートなのです。
老朽化した構造物の浴室は、その形状や材質、場所によって
リフォームではどうにもならないような物件もあります。
しかし、バスメイクさんの手にかかれば、
浴室全体のリフォームをするよりも格段に安い価格で補修ができるうえ、
「他社でサジを投げられた案件」でも何とかしてもらえるという、
いわばお風呂周りの「匠」といっても過言ではない存在です。
ところがこの津田さん、
施工実績で県内ナンバー1の実績を誇るエキスパートであり、
その技術力も施工数も申し分ないのですが、そこはやはり職人さん。
「素晴らしい商品を持っている人に限って売るのが下手」という法則にもれず、
思うように集客ができずにいました。
そんな津田さんの目下の課題は、法人客探しでした。
つまり、ビジネスパートナー探しです。
けれども津田さんには、どうしても譲れない部分がありました。
それは、「下請けなんだから、元請けの言うことは何でも聞け」
というような業者とは付き合いたくないということでした。
そこでまず津田さんは、
・無理な工期には応じられません。
・下請なんだから何でも言うことを聞け、という方とは仕事しません。
・法外な値引き要求には応えられません。
こうした断りを、自社の案内にしっかりと明示することにしたのです。
つまり、イヤなお客さんとは付き合わないことを宣言したのです。
そんな津田さんのもとに、大きなチャンスが舞い込みます。
この契約が無事にまとまれば、今後の仕事がかなり安定するとのこと。
どうしてもモノにしたいということで、ご相談をお寄せいただいたのです。
おおまかな交渉のコツは別にアドバイスをさせていただいたものの、
津田さんが特に心配されていたことは、
「あんなことを書いたら、高圧的な態度だと取られかねないのではないか?」
「意図せず、横柄なヤツだと思われてしまうのではないか」
というものでした。
「あんなこと」とは、前述の自社の案内に掲載した「宣言」です。
たしかに津田さんは根っからの職人さん。
メールの文面は簡素だし、話し方もちょっとぶっきらぼう。
津田さんのことを良く知らない人からすると、
ちょっと気難しそうなイメージを持たれているかもしれませんでした。
そこにあの宣言です。
相手方に、あらぬ誤解を生んでしまう懸念はありました。
しかし、津田さんの思いも承知していた私は、
ほんの少しだけ書き加えていただくことにしました。
たとえば、こんな風です。
・主張=無理な工期には応じられません。
・理由=なぜなら、無理な工期を約束してしまったがゆえに、
工事のクオリティを落とすことは本意ではないからです。
また、それでお客様に喜んでいただけない結果になってしまったら、
あたなにとっても私にとってもお客さまにとっても不幸だからです。
・エピソード=事実、こういうことがあったんです。
あれは3か月前のことです。
●●という団地の浴槽修理をした際、・・・。
つまり、それぞれの宣言を、
【宣言(主張)】+【理由(根拠)】+【エピソード(裏付け)】
というセットにして、書き直していただくことにしたのです。
それから連絡がなくなった津田さんの結果がどうだったのかは分かりません。
しかし、どれほど言葉を尽くしても、100%の思いを届けることは
できません。だからこそ、あなたはあなたの思いを伝えることに、
最善を尽くしてほしいのです。
「イヤなお客さんと付き合わなくていい方法」は、
「自分に期待を寄せてくれるお客さんに精一杯応える方法」
でもあります。
あなたの発するメッセージは、誤解なく相手方に伝わっていますか?
追伸:
それから2か月ほどたった今日、突然のメールが届きました。
「以前ご相談させていただいた、●●県営住宅の浴室修繕の件ですが、
お陰様で今日契約となりました。本当にうれしいです。 」
言葉少なに書かれたそのメールは、相変わらず職人さんのそれでした。
しかし、わたしにとっては何物にも代えがたいものでもありました。
まずはおめでとうございました。
この場を借りてお祝い申し上げます。
マーケティング・トルネードの巽です。
今回も、クライアントさんからご相談頂いた
事例を紹介してみたいと思います。
石川県で、浴槽の再生事業を専門にされている、
バスメイクの津田さんというクライアントがいます。
浴槽の再生事業とは、早い話がお風呂周りの修理屋さん。
でも、普通の修理屋さんとは、ちょっと違うんです。
旅館やホテル、賃貸物件など、何十年間も利用されて老朽化した浴室や、
すでに修理の施しようがないほどに損傷してしまった浴槽本体を、
特殊な再生技術を使って、まるで新品と見間違えるような
補修作業してしまうエキスパートなのです。
老朽化した構造物の浴室は、その形状や材質、場所によって
リフォームではどうにもならないような物件もあります。
しかし、バスメイクさんの手にかかれば、
浴室全体のリフォームをするよりも格段に安い価格で補修ができるうえ、
「他社でサジを投げられた案件」でも何とかしてもらえるという、
いわばお風呂周りの「匠」といっても過言ではない存在です。
ところがこの津田さん、
施工実績で県内ナンバー1の実績を誇るエキスパートであり、
その技術力も施工数も申し分ないのですが、そこはやはり職人さん。
「素晴らしい商品を持っている人に限って売るのが下手」という法則にもれず、
思うように集客ができずにいました。
そんな津田さんの目下の課題は、法人客探しでした。
つまり、ビジネスパートナー探しです。
けれども津田さんには、どうしても譲れない部分がありました。
それは、「下請けなんだから、元請けの言うことは何でも聞け」
というような業者とは付き合いたくないということでした。
そこでまず津田さんは、
・無理な工期には応じられません。
・下請なんだから何でも言うことを聞け、という方とは仕事しません。
・法外な値引き要求には応えられません。
こうした断りを、自社の案内にしっかりと明示することにしたのです。
つまり、イヤなお客さんとは付き合わないことを宣言したのです。
そんな津田さんのもとに、大きなチャンスが舞い込みます。
この契約が無事にまとまれば、今後の仕事がかなり安定するとのこと。
どうしてもモノにしたいということで、ご相談をお寄せいただいたのです。
おおまかな交渉のコツは別にアドバイスをさせていただいたものの、
津田さんが特に心配されていたことは、
「あんなことを書いたら、高圧的な態度だと取られかねないのではないか?」
「意図せず、横柄なヤツだと思われてしまうのではないか」
というものでした。
「あんなこと」とは、前述の自社の案内に掲載した「宣言」です。
たしかに津田さんは根っからの職人さん。
メールの文面は簡素だし、話し方もちょっとぶっきらぼう。
津田さんのことを良く知らない人からすると、
ちょっと気難しそうなイメージを持たれているかもしれませんでした。
そこにあの宣言です。
相手方に、あらぬ誤解を生んでしまう懸念はありました。
しかし、津田さんの思いも承知していた私は、
ほんの少しだけ書き加えていただくことにしました。
たとえば、こんな風です。
・主張=無理な工期には応じられません。
・理由=なぜなら、無理な工期を約束してしまったがゆえに、
工事のクオリティを落とすことは本意ではないからです。
また、それでお客様に喜んでいただけない結果になってしまったら、
あたなにとっても私にとってもお客さまにとっても不幸だからです。
・エピソード=事実、こういうことがあったんです。
あれは3か月前のことです。
●●という団地の浴槽修理をした際、・・・。
つまり、それぞれの宣言を、
【宣言(主張)】+【理由(根拠)】+【エピソード(裏付け)】
というセットにして、書き直していただくことにしたのです。
それから連絡がなくなった津田さんの結果がどうだったのかは分かりません。
しかし、どれほど言葉を尽くしても、100%の思いを届けることは
できません。だからこそ、あなたはあなたの思いを伝えることに、
最善を尽くしてほしいのです。
「イヤなお客さんと付き合わなくていい方法」は、
「自分に期待を寄せてくれるお客さんに精一杯応える方法」
でもあります。
あなたの発するメッセージは、誤解なく相手方に伝わっていますか?
追伸:
それから2か月ほどたった今日、突然のメールが届きました。
「以前ご相談させていただいた、●●県営住宅の浴室修繕の件ですが、
お陰様で今日契約となりました。本当にうれしいです。 」
言葉少なに書かれたそのメールは、相変わらず職人さんのそれでした。
しかし、わたしにとっては何物にも代えがたいものでもありました。
まずはおめでとうございました。
この場を借りてお祝い申し上げます。
株式会社マーケティングトルネード
巽大平
| «前へ | 次へ» |
 ログイン
ログイン